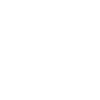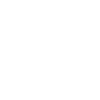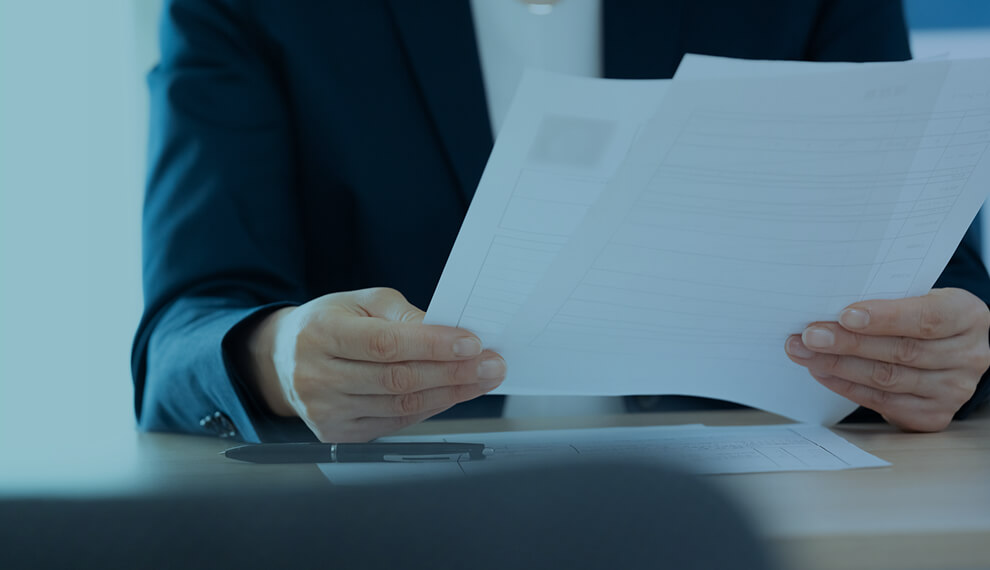AIの普及で法律相談はどのように変わるか?【受任率を高めるために意識すべきこと】
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の飯塚泰之でございます。
AIで法律事務所を探す人が徐々に増加中
最近、先生方とお話をしていると
「AIで法律事務所を探して相談に来られた方がいた」
「依頼者がAIにも相談していると言っていた」
というケースをお聞きすることが増えてきました。
実際に、WEBサイトのアクセス状況を分析してみると、GeminiやChatGPT、Perplexityなどの生成AIからの流入が獲得できていることが分かります。私が確認している限りでは、どの事務所様も、生成AIからの流入は、全体のアクセス数に対して「0.5%程度」と極めて小さい割合ではありますが、滞在時間が長かったり、コンバージョンが記録されていたりと、問い合わせ確度が高いユーザーがアクセスしていることがわかってきました。
実際にSNSやブログなどを検索してみると、弁護士に依頼せずにAIで自分で書面を作成して調停に対応しているような方の投稿が見つかることもあります。
こうしたAIの影響は、今後大きくなっていくことはあっても小さくなっていくというのはあまり考えられません。
AIに関しては、法律実務への影響や活用方法などが取り沙汰されることが多くありますが、本コラムでは、【AIが普及していくことで法律相談はどのように変わるか?】ということをテーマにお送りしたいと思います。
受任率を高めるために、面談の進め方を工夫したいとお考えの先生方はぜひお読みください。
AIによって情報の非対称性が薄れ、単なる情報提供の価値は下がる
生成AIの利用が一般化していくことによって、相談者のリテラシーが大幅に向上することが真っ先に考えられます。
WEBサイトが普及したことで法律相談の前に下調べをしてから相談に来る方が多くなったように、AIによって複雑で個別具体的な事案に合わせた最適な情報を調べることができるようになり、いままで以上に相談者は、事前に必要な情報を調べることが容易になります。
弁護士をはじめとする専門職である方々の相談は、専門知識を有している弁護士と有していない相談者のあいだの情報格差が大きいため、これまでは”情報を提供する”ことそれ自体に価値がありました。しかし、そうした情報提供は今後AIが簡単にやってくれるようになります。離婚でも、相続でも、あるいは企業法務分野においても、ただ単に情報を伝えるということの価値は確実に下がっていきます。
「何をすべきか?」を示す提案型の法律相談へのシフトが重要に
AIの浸透によって、情報を解説し教えることの価値が下がる一方で、持ちうる情報の中からより良い戦略判断を行うことが法律相談では重要になっていくものと考えられます。
法律相談において、最も大事なことは「○○法の何条に該当するか」や「どの判例に相当するか」ではありません。
相談者にとっては、そうした情報は乱暴な言い方をすれば些事であり、一番求めているのは、結局なにをすべきなのか?という点です。
以前、受任率が高い先生に、
「受任率を高めるためにまず何をすべきでしょうか」とお聞きしたところ、
「相談室に六法を持ち込まないこと」とお答えいただいたことがあります。
大事なことは、法律の条文ではなく、相談者の悩みを解決するために何が必要なのかを示し、希望を見せてあげることだという趣旨でした。
そして、AIで専門知識の収集が容易になる一方で、「わかる」と「できる」はまったく違います。法律知識を多く得たからといって、上手く交渉ができるわけではありません。
常に変わりゆく状況の中で、目的達成のためにどのような主張を行い、どこまで譲歩を示すかということを戦略立てて交渉していくというのは、先生方が多くの事件を通して培ってきたものであり、それこそが、弁護士の腕の見せ所でもあると思います。
相談者が求めるニーズを押さえながら、「あなたの望みを叶えるには、結論こうすべきです」と端的に示すことが、相談の満足度を上げ、受任に繋げるために必要なこととなります。
なぜAIではなく弁護士に依頼するのか?
AIと人間の違いは、24時間いつでもどこでも、どれだけでも、文句を言わずに答えてくれるということです。愚痴や弱音もAIは受け止めてくれます。生身の人間よりも上手に感情に寄り添って前を向くためにアドバイスをしてくれます。有料プランでもせいぜい月数万円しかかかりません。
その中でも、なぜ弁護士という第三者に依頼をするのか、その価値はどこあるのかということに対して訴求ができていない相談の進め方では、今後受任率は下がっていきます。
また、AIに聞けば、その分野に詳しそうな法律事務所をいくらでも教えてくれます。
「他事務所と比較検討されることは当たり前(これまでよりもさらに増える)」としたうえで、相談を組み立てていくことが必要になっていきます。
まとめ
ここまでお読みいただきありがとうございました。
上記の内容は、あくまで私の考察ではありますが、AIがいつでも・どれだけでも・嫌がらずに答えてくれる時代に、法律相談の意義やどこに重点を置くべきなのかは、間違いなく変わっていくのだろうと思います。
受任を増やすために、面談の進め方に悩みをお持ちの先生は非常に多いです。
私もこれまで多くの事務所様と模擬面談(ロールプレイング)を実施し、
「この伝え方だと依頼したいと思えないな…」
「こんな提案されたら、確かにお願いしたくなってしまうな…」
「先生にはもっと良いところや強みがあるのに、伝えきれていないな…」
など色々と感じることがございました。
AIが普及する中で、法律相談の進め方やスタイルを変えないままでは受任率が下がってしまう可能性は大きくなります。
今後の面談や受任率に不安があるという場合には、ぜひ私たちと一緒にロールプレイングを通して、受任率を上げるためのトレーニングをしていきましょう。